新年度が始まってしばらく経ち、新しい環境にも慣れたはず。
それなのに、子どもが最近「学校に行きたくない」と言い出した…。
このような経験、ありませんか?
「学校で何かあったのかな」
「甘えじゃないの?」
心配になる気持ちと、どうしたらいいかわからなくなる気持ちになりますよね。
特に、朝のバタバタする時間に「行きたくない」が始まると、親も焦ったりイライラしたりしてしまいます。
だからといって「行きたくない気持ちを否定する」「無理やり行かせる」のはNG。
その『行き渋り』は、子どもの心のSOSかもしれないからです。
このSOSを見逃すことで、不登校につながる可能性があります。
子どものSOSに寄り添うために、子どもが行き渋るときの原因や、家庭でできる対応、学校との連携の仕方などを元教員の視点から解説します。
行き渋りは「子どもからのSOS」

行きたくない理由を聞いても要領を得ない…
先生に聞いても、学校では元気に過ごしているそう…
誰に聞いても理由がはっきりしないと、「ただの甘えなのでは?」と思いますよね。
でも、「うまく言えない」だけで、内面では不安や緊張と闘っていることもあります。
そして、一見元気そうだから、周囲には気付かれにくい。
その、「わかってもらえない」ことが子ども自身を苦しめている可能性があるのです。
「何か理由があるのかもしれない」と受け止めることが、子どもに寄り添う第一歩です。
子どもが学校を行き渋る理由とは?
一口に行き渋りといっても、年齢や学年、環境によって理由はさまざまです。
子ども自身が「これ」と認識していない可能性や、どれか一つではなく、複雑に絡み合っている場合も大いにあります。
ここでは、学年ごとの傾向をもとに、考えられる原因について解説します。
低学年:親から離れたくない(母子分離不安)
「母子」とありますが、母親に限りません。
・自分のことを1人でできるか不安になる
・新しい環境に慣れていない
こうした理由から家の人と離れることに強い不安を感じます。
特に、学校は園と比べると保護者の出入りが少ないので、その不安が現れることが多いのです。
低学年:学校生活の変化によるストレス
入学や進級によって生活スタイルが変わり、戸惑う子は多いです。
幼稚園・保育園から入学した新1年生は、「学校」そのものが初めてだらけ。
・園時代とは違うルールに慣れなければならない
・座る時間が長く、自由に遊べる時間は短い
・集団で行動することに慣れない
どれだけ入学を楽しみにしている子でも、張り切っている子でも、環境が変わる時期は少なからず「無理してる」状態になります。
適応するまでに時間がかかる子にとっては、学校に行くことがつらく感じてしまうものです。
低学年:疲れや睡眠不足
成長するとともに体力もついてくるものですが、まだ小さいうちは疲れがたまりやすいです。
・毎日17時まで学童に行く
・習い事などで寝るのが遅くなる
こうした理由で「今日は休みたい」、「学校に行くと疲れる=行きたくない」という思いにつながることがあります。
中~高学年:友達関係の悩み
中学年くらいになると、友達関係の複雑さが現れてきます。
・「仲良しの子とトラブルがあり、行きたくない」
どちらも行き渋りの理由としてあり得ます。
中~高学年:学習面の不安
学年が上がると、学習の内容が難しくなり、授業のペースも早くなります。
子ども自身の得意不得意がはっきりしたり、友達と比較して苦手意識をもったりする時期でもあります。
そのため、
・テストの点数が気になる(周囲と比べてしまう)
といった悩みを抱え始めるのです。
【こちらの記事では「家庭での学習を支える関わり方」を解説しています】
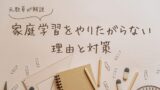
高学年:責任によるプレッシャー
下級生のお世話を任されたり、委員会などでリーダーを務めることになったりと、高学年になると何らかの役割を受け持つ場合があります。
・完璧でなければ、と思ってしまう
「しっかりやらないと」と思う子はこういった不安につながりやすく、学校に行くのが憂鬱になるケースも多いです。
全学年:先生がこわい、合わない
・先生が理不尽だ
・授業がおもしろくない
現場でよく耳にしていました。
「先生がこわい」は、低学年、「先生が理不尽だ」「人によって態度が違う」は高学年で多く見られる状態です。
もちろん、実際にそういった場合もありますが、声のトーン、ちょっとした態度などから苦手意識が生まれることもあります。
行き渋りの主な原因まとめ
・母子分離不安
・環境への不適応
・生活リズムの変化による疲れ
・先生がこわい【高学年】
・友人関係
・学習などのプレッシャーや不安
・先生と合わない
子どもの年齢や学年に応じて、行き渋りの理由は異なります。それぞれの背景を理解し、適切な対応を心がけましょう。
行き渋りは不登校の前兆となることも
文部科学省の調査によると、不登校は年々増加の傾向であることがわかります。
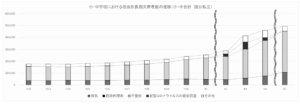
引用:令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果 本体資料
引用:令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果 概要
この調査によると、小中学生の不登校理由として「やる気がでない」「不安」が約半分を占めています。
また、23%は「生活リズムの不調」を理由としていることがわかります。
約10年前の調査では、不登校の理由として「友人関係」が約半数だったことを踏まえると、年々「無気力」「不安」を感じる児童生徒が増えており、それが不登校へつながっているということです。
はじめはちょっとしたサイン。
でも、その行き渋りを放置すると、不登校へと発展する可能性があるため、早期の対応が重要です。
子どもが行き渋った時に家庭でできる対応

行き渋りには、「最近元気ないな」とその兆候が表れる場合と、「元気そうに過ごしていたのに」といういわゆる「急に」現れる場合があります。
ここでは、子どもが学校に行きたくないと言ったときに家庭でできる対応と、避けてほしい対応について解説します。
子どもの気持ちに寄り添う
「学校に行きたくない」と言われたら、まずは否定せずに話を聞いてあげましょう。
子どもが理由を話すことができる状態であれば、その悩みを共有し、共感の姿勢を見せます。
「家族が聞いてくれた」「わかってくれた」という安心感を与えることが大切です。
生活リズムの見直し
夜しっかり寝ているか、朝はすっきり起きているかなど振り返ってみて、必要があれば生活リズムを整えましょう。
朝、すっきり起きられないときはそのまま「学校に行きたくない」という気持ちにつながりやすいです。
気持ちを切り替える働きかけ
学校生活の不安を抱えている場合、自己肯定感が下がっている可能性があります。
家庭でのお手伝いをお願いし、達成感を味わわせることや、「できた」というポジティブな感情を生むことを目指します。
子ども自身が好きなことに取り組めるようにサポートし、自己肯定感を高める働きかけも有効です。
「頑張れ」は逆効果?避けたいNG対応
行きたくない気持ちを否定する
家で元気そうに過ごしていると「甘えているだけじゃないのか」と思ってしまいますよね。
「頑張って行ってらっしゃい」
このような声かけは、子どもにとって「受け止めてもらえなかった」「言っても無駄だ」と思ってしまう可能性があります。
特に否定的な言葉は、信頼関係を損なってしまうので、注意が必要です。
登校を無理強いする
行けばなんとか1日を過ごす子も多いです。
でも、それは子どもが無理して耐えている姿かもしれません。
子どもが行きたくない理由を無視して無理に登校させると、さらにストレスを感じたり、その反動がきたりして、不登校につながる恐れがあります。
「学校には行かなきゃだめ」「休むなんてだめ」と、頭ごなしに否定するのはNGです。
理由を問い詰める
「行きたくない」「学校やだ」そんな言葉の裏には、思いがあります。
でも、それをうまく説明できなかったり、言いたくなかったりすることもあるのです。
子ども自身も気持ちが整理できていなく、なぜそのような感情になるのかわからない場合も。
大人は「どうしたの?」「何かあったの?」と聞きたくなりますよね。
子どもがそれをうまく言えないときは、行きたくない気持ちを受け止めることを優先します。
「理由がないなら行きなさい」と否定しないように気を付けましょう。
家庭でできるサポートとNG対応
◎子どもの気持ちを受け止める
◎自己肯定感を高める
◎生活リズムの見直し
△甘えと決めつける
△無理やり登校させる
△理由を問い詰める
→親子の信頼関係が崩れ、自分の気持ちを言えなくなってしまう
→不登校へとつながる可能性がある
子どもの行き渋りが続く時の相談先

行き渋りがあったときには、まず学校に連絡をすると思います。
「理由がわからないのに、なんて連絡したらいいの?」
「行きたがらないなんて、先生に言いにくいかも…」
そう思う保護者も少なくありません。
ここでは学校への相談の仕方や内容、ほかに頼れる機関について解説します。
まずは学校やスクールカウンセラーに
学校への相談は、ありのままでOKです。大事なのは状況を共有することです。
一時的なものなのか、隠れた長期的な原因があるのかも含めて、学校と保護者で知り得る情報を共有しましょう。
すぐに理由に見当がつかない場合でも、辛そうなときに保健室や別室で学習するなど、校内でのサポート体制についても相談することができます。
行き渋りの原因が担任である、もしくは担任には言いにくい理由であるときは、直接担任に連絡を入れなくても構いません。
保健室の先生、教頭、校長など別の職員に相談することも可能です。
また、学習の遅れが気になっていたり、集団生活への不適応が見られたりしていて、個別な支援を相談したい場合は、各学校にいる「特別支援コーディネーター」の職員と話をするというのも一つの方法です。
特別支援教育コーディネーターとは、各学校における特別支援教育の推進のため、主に、
・特別支援教育に係る校内委員会・校内研修の企画・運営、
・関係諸機関・学校との連絡・調整、
・保護者からの相談窓口
などの役割を担う教員。校長が指名し、校務分掌に位置付けられる。
学校からスクールカウンセラーへの相談を提案されることもあります。
スクールカウンセラーは専門的な知識がある職員です。
子どもだけ、保護者だけ、という利用もできますので、気になる方はつないでもらえるように言ってみてください。
公的な機関を活用する
「外部の人にも相談したい。」
そんな時に頼れる相談先を知っておくと一安心です。
①教育支援センター(適応指導教室)
各自治体が設置している「教育支援センター(適応指導教室)」は長期間登校できていない子に対して、教科指導や体験活動を保障する場です。
保護者の相談、カウンセリングも行っています。
②厚生労働省「こころの相談窓口」
厚生労働省の「こころの相談窓口」には不登校専用の窓口があります。
保護者からでも、本人からでもかけられるダイヤルです。
参考:不登校やいじめ、ひきこもりなどの相談窓口|こころの相談の窓口について|困ったときの相談先|こころもメンテしよう ~若者を支えるメンタルヘルスサイト~|厚生労働省
③夜眠れない、体に不調が現れる場合は、病院の受診も検討しましょう。
▼受診すべきか迷う方に、こちらの記事が参考になります。
不登校のとき心療内科に行くべきかの見極め方!受診のデメリットとは|【復学支援専門・公認心理師監修】エンカレッジ公式ブログ「エンブロ」
まとめ|行き渋りの理由を知って、適切なサポートを
子どもが行き渋ると、保護者も焦りや不安が生まれますよね。行き渋りは、一時的である場合や、発達とともに落ち着いてくることも多いです。
大切なのは「甘え」と決めつけて気持ちを否定したり、無理に登校させたりしないこと。
一旦気持ちを受け止めてから、今後の方針について考えていきましょう。
学校や関係機関も、子どもと保護者の味方です。一人で抱え込まず、周りを頼ってくださいね。

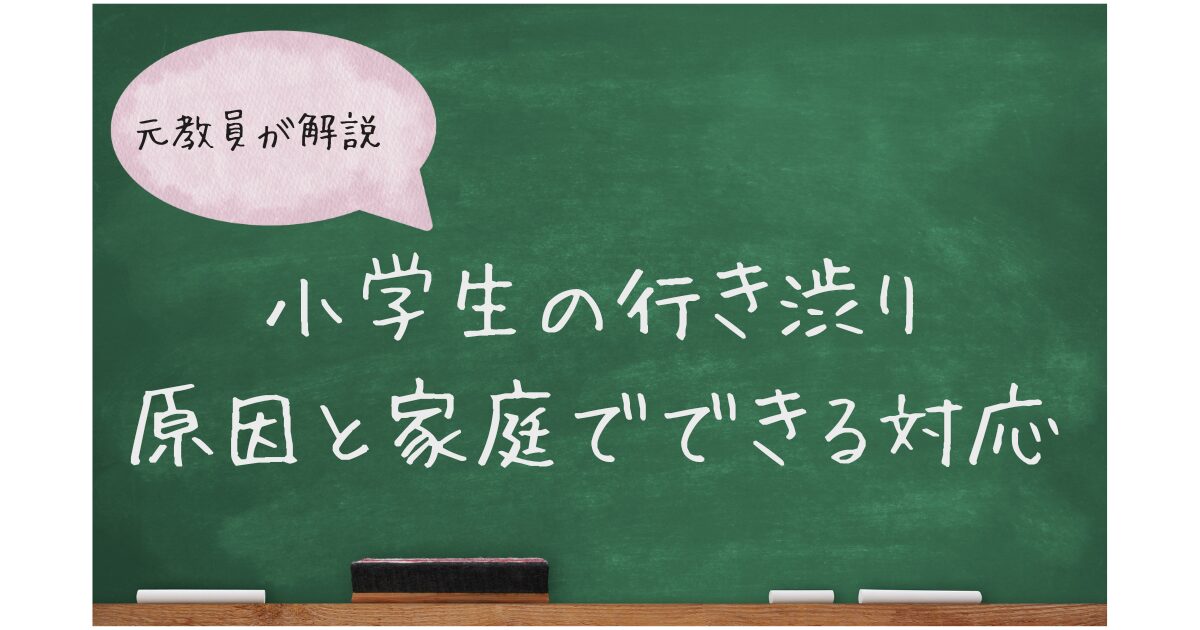

コメント