9月1日は「防災の日」。
学校でも避難訓練や特別活動を通して、防災について考える機会が設けられています。ただ、防災についてどう子どもに伝えたらいいのか、若手の先生にとっては悩ましいテーマかもしれません。
本記事では、防災の日の由来や学校で防災に触れる意義を整理しながら、朝の会で話せる具体的な内容例や注意点を紹介します。
「防災の日、何を話せばいいのか分からない」そんなときにすぐ活用できる内容になっているので、ぜひ実践に役立ててみてください。
防災の日とは?

「防災の日」は1960年(昭和35年)に制定され、毎年9月1日と定められています。背景には、1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災があり、この震災を教訓として防災意識を高めることが目的とされています。
また、日本は地震だけでなく台風や豪雨など自然災害が発生しやすい国です。
9月1日は立春から数えて210日目にあたり、昔から「台風が来襲しやすい時期」とされる「二百十日」にあたることも、防災の日に定められた理由の一つとされています。
さらに、8月30日から9月5日までは「防災週間」とされ、全国で防災に関する啓発活動や訓練が実施されています。
参考:政府広報オンライン(防災の日 | 政府広報オンライン)
参考:東京消防庁「防災の人二百十日」(防災の日と二百十日 | 東京消防庁)
参考:防災週間の期間について : 防災情報のページ – 内閣府
学校で防災教育に触れる重要性
学校は、子どもが長い時間を過ごす生活の場であり、地域の避難所としての役割も担っています。
避難訓練や学級活動のような改まった場に加えて、担任が日常的に短く触れることも、子どもにとって大切な学びの機会になります。
防災教育も学校教育の一部

学校でも、避難訓練や学級活動、「社会」「理科」といった各教科を通して、防災教育において横断的に取り組むことが求められています。
防災教育の主なねらいとしては、以下の通りです。
- 自然災害の基本知識
- 住む地域の特色
- 日常の備えについての実践意欲
- いざというときの判断力
- 復興支援への関心
これだけ見ても、「避難訓練」だけで養うことは不可能といっていいでしょう。
そのため、学年に応じて普段から取り扱うことが重要になります。
参考:文科省・学校防災のための参考資料「生きる力」を育む防災教育の展開
授業以外の時間にも触れる意味
防災教育といっても、必ずしも改まった機会に行う必要はありません。
むしろ、ふとした時の先生の言葉の方がすっと心に入っていく場合もあります。
先生自身が防災教育を「特別扱い」せず話題にすることで、子どもたちにとっても触れる機会が増え、日常生活の中に根付いていきます。
防災について子ども向けに話すときのポイントや注意点

災害や被災についての話は、取り扱い方によっては子どもたちに不安を植え付けてしまいます。
「怖がらせる」のではなく「考える」時間にするために気を付けたいポイントについて解説していきます。
短い時間でも話題にする機会を増やす
1時間かけてじっくり考える時間も大事ですが、短い時間で触れることも日常化するためには有効です。
朝の会の時間を活用するなら 3〜5分程度でも十分。
ちょうど9月1日前後には「防災週間」もあるので、1日1テーマ程度に絞って伝えると、子どもにとって負担なく受け止めやすくなります。
子どもの発達や実態に合わせて話す
不安をあおる時間にしない
防災教育の教材には、動画や震災の記録映像などもありますが、子どもによっては必要以上に恐怖心を抱いてしまうこともあります。
「恐怖をあおる」のではなく「安心のための準備」として、慎重に取り扱いましょう。
学年や子どもの様子に十分に配慮することが重要です。
「正解」として扱うのではなく、考える力をつける
避難や備えの仕方に「絶対の正解」はないことを大前提として伝えることも重要です。
災害時の状況によって最適な行動は変わります。「学校でこう教わったから」だけではなく、状況によってとるべき行動も異なるという前提を共有するようにしましょう。
防災の日に朝の会で使える話の例

防災の日だからといって、特別な教材を準備したり長時間話し込んだりする必要はありません。朝の会でほんの数分触れるだけでも、子どもたちにとっては大切なきっかけになります。
ここでは、すぐに取り入れられる話題の例をいくつか紹介します。
自然災害についての学び
地震・火事・台風など、災害によって行動や対策の仕方は異なります。
「地震のときはどうする?」「火事のときはまず何をする?」といった問いかけを交えながら、基礎的な知識に触れる時間をつくるのも効果的です。
また、住む地域によって起きやすい災害にも違いがあるため、自分たちの住む地域に合わせて話すと、より自分の生活と結びつきやすくなります。
合言葉を確認
避難訓練でよく使われる「おかしもち(おさない・かけない・しゃべらない・もどらない・ちかづかない)」など、学校ごとに設定されている合言葉を確認します。
大人がそばにいないときでも子ども自身で安全に行動できるように、繰り返し意識させることが大切です。
◎×クイズで判断力を
イラストやスライドを使ってクイズ形式にすると、低学年でも防災を身近に感じやすくなります。
例えば「地震がきたらベランダに出る→〇か×か」など、判断に迷いそうな場面を取り上げることで、「いざというときの判断力」を養えます。
防災を家庭生活につなげて考える
「防災リュックの中身を知っている?」「自分の家の避難所はどこ?」「おうちの人と待ち合わせを決めてある?」といった問いかけをすると、家庭や地域とつながる学びになります。
子どもに宿題のように持ち帰らせたり、通信で取り上げたりすると、家庭での話し合いのきっかけにもなります。
防災の日×避難訓練で効果的な防災教育を

防災の日に合わせて避難訓練が設定されている学校は多いですが、より効果的なものにするには「事前」「事後」の指導が大切です。
ここでは具体的な声掛け例と目的を紹介します。
事前に問いかけると意識が変わる
避難訓練は、何度も経験するうちに「ただの行事」として流れてしまいがちです。
だからこそ、次のような事前の問いかけで、避難訓練の意味を確認しておきましょう。
- なぜ訓練をするのか
- もし誰もいないときに災害が起きたらどうするか
自分の身を守る行動だと意識できるだけで、同じ訓練でも得られる学びは大きく変わります。
※例えば東日本大震災の際には、日ごろからの訓練をもとに「自分の判断で避難した中学生」の例もあります。こうした事例を紹介し、改めて避難訓練の必要性を話し合うことも効果的です。
参考:総務省消防庁/3.釜石の奇跡 – 防災危機管理eカレッジ
振り返りで次につなげる
訓練後には「落ち着いて行動できたか」「合言葉を意識できたか」など、安心につながる行動を具体的に取り上げて共有すると効果的です。
小さな成功体験を言葉にすることで、子どもは「こうすればいいんだ」と自信を持てます。繰り返し評価されることで、防災への前向きな意識が自然と育っていきます。
まとめ|防災の日をきっかけに子どもと考える

防災の日は、国の指針にも位置づけられた大切な機会です。いつ起きるかわからない災害に対して「備える力」と「行動する判断力」を養っていくことが求められています。
避難訓練のような場だけでなく、朝の会などで先生が短く触れることも子どもにとって大きな意味があります。
今年の防災の日、朝の会で子どもに伝えたい一言を、ぜひ準備してみてください。

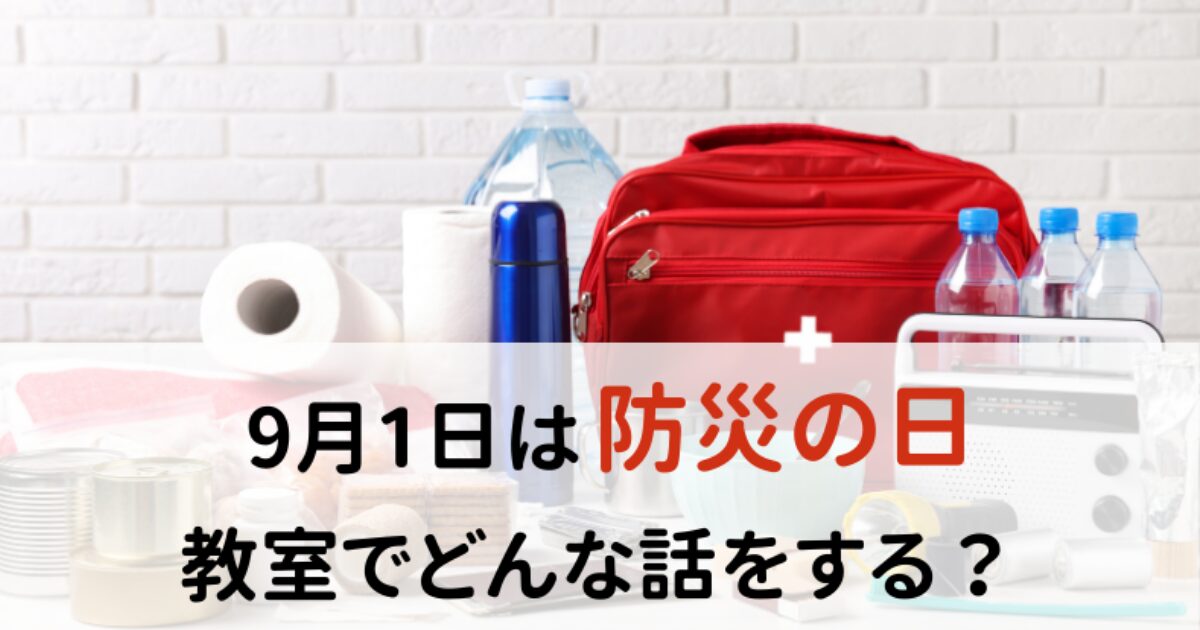


コメント