勉強したがらない小学生に!低学年向け「遊び×学び」の家庭学習アイデア
「学校の宿題だけで足りてるのかな」
「勉強させたいけど、うちの子勉強嫌いだし…」
そんなふうに悩む保護者の方は多いのではないでしょうか。
「勉強させなきゃ」と思って関わっても、子どもが「やらされている」と感じる学習は、なかなか長続きしないし、逆効果。
勉強を嫌がってバトルになった経験がある方もいると思います。
この記事では、元教員の視点から、机に向かうのが苦手な子どもでも、家庭で楽しく学習できるアイデアを具体的に紹介します。
宿題以外の勉強は必要?家庭学習の意味と目安

プリントやタブレットで、学校から宿題が出ることがあると思います。
でも、中には「これだけ…?」「ほかにも何かやらせるべき?」と感じる保護者の方もいるのではないでしょうか。
宿題以外の学習が必要かどうかは、子どもの学習ペースによって変わってきます。
その理由を、家庭学習の意味と関連付けながら解説していきます。
家庭学習の目的とは
家庭学習の目的は、学力を高めるだけではありません。
もう一つ大切なのは「学習習慣を身に付ける」ことです。
こうした積み重ねが、習慣作りに大切です。
学校から出ている宿題が多い、毎日計画的に取り組めているといった場合は、家庭独自の学習を無理に増やす必要はありません。
でも「宿題がすぐに終わってしまった」「何もすることがない」ときは、短時間でも学習時間を確保すると、家でも勉強することが日常化していきます。
「学年×10分」が目安!大事なのは続けられるペースづくり
家庭学習の時間としてよく言われるのが「学年×10分」。
たとえば1年生なら10分、3年生なら30分。これは「無理なく毎日続けられる基準」として、学校現場でも意識されています。
ただ、これはあくまで「目安」。
重要なのは時間の長さよりも「毎日学ぶリズム」をつくること。
たとえば、タイマーをセットして「時間で区切る」方法が合う子もいれば「今日はここまで」と「量で区切る」方がやりやすい子もいます。
子どもが勉強したがらない理由と親の関わり方

「宿題以外にも何かやらせたいけど、子どものやる気がない…」と悩んでいる保護者の方は多いです。
無理にやらせても意味がないとは思いつつ、つい口を出したくなりますよね。そして親子げんかに発展…という話も、珍しくありません。
「勉強しなさい」と言えば言うほど、子どもはますますやる気をなくしてしまう。
でも、家で勉強したがらない理由は「勉強嫌い」だけではないのです。
たとえば、こんな本音があることも。
・勉強よりしたいことがある
・勉強が苦手で一人で取り組めない
・×をつけられるのがイヤ
こんな状態で机に向かわせても、集中できずにだらだらしてしまいます。
そしてさらに口を出してしまい、バトル再開…と悪循環に陥ることもあります。
家庭学習の声掛けなどはこちらの記事をご覧ください。
【関連記事はこちら↓】
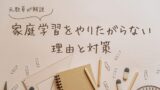
勉強したがらない子どもでも取り組みやすい「遊び×学び」のアイデア5選

勉強したがらない子どもでも、遊びを切り口にすると自然と学習に向かえることがあります。
ポイントは、「楽しそう!」と思える工夫と「勉強っぽさ」を感じさせないこと。
ここでは、できるだけ道具を使わない「遊び×学び」のアイデアを5つ紹介します。
しりとり|語彙・発想力が育つ王道遊び
親の関わり:あり(一人しりとりの場合はなし)
「しりとりが勉強になるの?」と思うかもしれませんが、低学年にとっては大事な言葉の学習です。
口頭でのやり取り、文字に起こす、カタカナしばりなどバリエーションを工夫すれば、語彙力や文字理解も深まります。
漢字たし算|クイズ感覚で、自然と漢字の構造理解に
親の関わり:あり
「糸+白+水=?」などと、漢字を分解してクイズ形式に。
部首を習っていない段階でも、楽しく取り組むことができます。
細かいルールは設定しなくても、漢字にのめりこむ姿につながれば十分。
子どももクイズを作るのが好きなので、出題者を入れ替えるのもおすすめです。
オリジナル図鑑作り|観察力や表現力を身に付ける
親の関わり:必要な場合あり
「恐竜が好き」「花に興味がある」と何かに熱中する子にぴったりです。
図鑑やタブレットで調べ、気に入ったものだけを集めて作る「自分だけの図鑑」。
好きなものだからこそ夢中になれるという「子どもらしさ」を生かした学習で「自由研究」にもつながります。
絵本作り|想像力・構成力・表現力など要素が盛りだくさん
親の関わり:必要な場合あり
創作が好きな子はぜひ試してほしいのが絵本作り。
ストーリーを考えて表現する過程には、多くの学びがあります。
家族が感想を伝えたり、冊子風にまとめてあげたりすると、満足感もあり「また作りたい!」と意欲アップにもつながります。
お店屋さんごっこ|実生活に結び付く大切な力
親の関わり:必要
お店屋さんごっこには、学びの要素が多く詰まっています。
たとえば「果物屋さん」をする場合には果物カードを書く段階で語彙力が身に付きます。
そして、買い物場面では数の理解や計算力が自然と育ちます。
生活力が培われる、貴重なごっこ遊びです。
家で簡単にできる「遊び×学び」アイデアまとめ
| 遊び | 学べる力 | 親の関わり |
| しりとり | 語彙力・発想力 | 少なめ |
| 漢字たし算 | 漢字の構造 | あり |
| オリジナル図鑑作り | 観察力・表現力 | 必要に応じて |
| 絵本作り | 創造力・構成力・表現力 | 必要に応じて |
| お店屋さんごっこ | 計算力・生活力 | あり |
机に向かわずできる「体験×学び」のアイデア5選
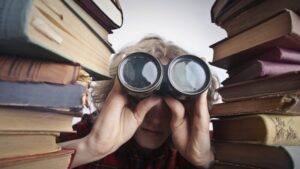
遊びの要素を含んでいても、なかなか気が向かない子には「体験型学習」がおすすめ。
実は、日常生活の中にも見方を変えると「学びの種」があふれています。
ここでは、紙も鉛筆も使わずにできる学びのアイデアを5つ紹介します。
買い物で計算力・計画力を
駄菓子屋さんで「100円分選んでいいよ」だけでも「計画力」「数量感覚」が身に付きます。
生き物を育てて観察力・責任感を育む
アサガオ・ミニトマト、カブトムシ、金魚など身近な動植物を育てる体験には、多くの学びがあります。
「昨日と何が違う?」と問いかけると、変化に気付く観察力につながります。
お世話に必要な情報を調べる過程では、自主性や情報収集能力も。
工作で「創造力」「集中力」を伸ばす
段ボール、空き箱などでする自由な工作は、手を動かしながら考えることそのものが学びです。
試行錯誤する中で、創造力や集中力、粘り強さが養われます。
夏休みは、普段なかなかできない大作に挑戦するチャンスでもあります。
クッキングで「数量感覚」「段取り力」を育てる
卵を割る、材料を混ぜるなど小さなお手伝いでも、数や手順を意識するようになります。
一人でレシピを見ながら作れたら、それはもう立派な学習。
旅行やお出かけを通して「社会への関心」を広げる
長い休みだからこそ、普段できない経験をするチャンスです。
帰省や旅行など、日常から離れる時間は子どもの視野を広げてくれます。
そこでしかできないこと、そこにしかないものに触れることで、地理・文化など社会的な関心が芽生えます。
まとめ|勉強したがらない子どもでもできる「学び方」はある

学びは、机の上にあるものだけはありません。
もちろん、学校の宿題をコツコツやることも大事ですが、机に向かうのが苦手な子どもには、遊びや生活体験を通したアプローチをするのも一つです。
「これも勉強なんだよ」と言葉をかけると「勉強=つらいもの」というイメージも変わっていくはず。
「楽しい」が入口になる学びで、子どもに合った学び方を探してみてください。

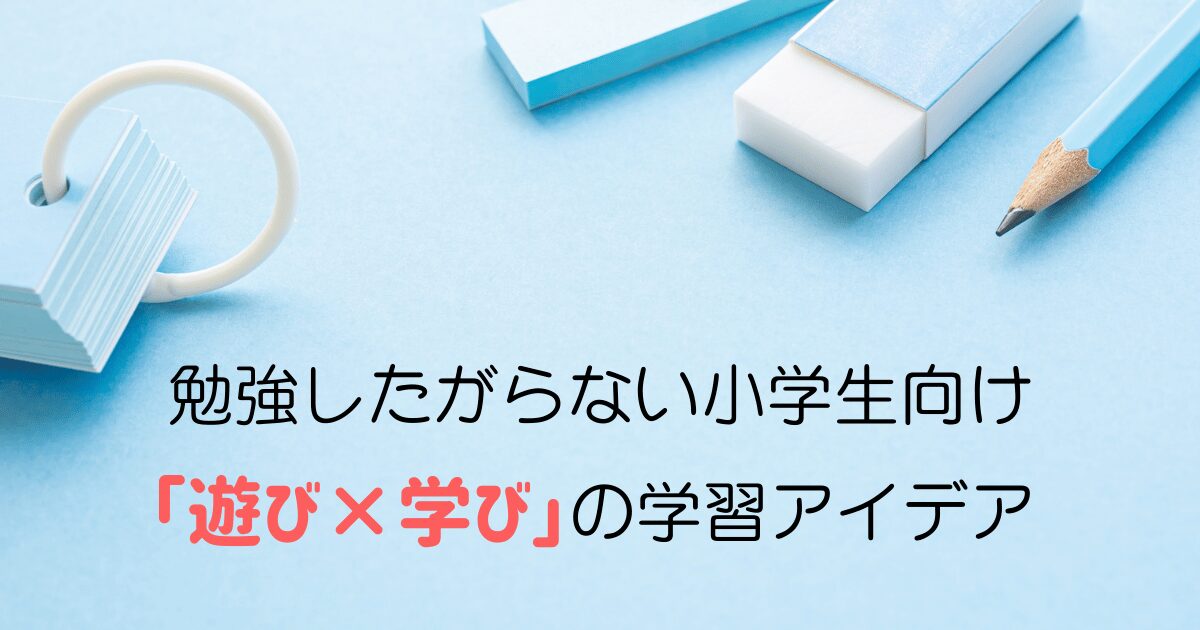


コメント