家庭学習を拒否?家で勉強したがらない子どもへの関わり方
「うちの子、なかなか机に向かわない」
「宿題をやるまでにバトルになる」
「毎日喧嘩ばかりで、疲れる…」
小学生の家庭学習について、こうして悩んでしまうこと、ありませんか?
自分から進んで机に向かってくれるのが理想的ですが、なかなかそうはいかないのが小学生。
だからといって、無理に机に向かわせるのは逆効果。
勉強したがらない理由を知って、それに合った関わりをすることで、親も子どもも今より心が軽くなります。
この記事では、低学年を多く担任した元教員が、小学生が勉強をしたがらないときの理由や、親も子も負担になりすぎない解決策について解説します。
なぜ家庭学習は必要?

低学年の保護者の方から、よくこのような相談を受けました。
たしかに低学年のうちは、学習内容が比較的やさしいので「勉強しないとついていけない」ことは少ないです。
でも、家庭学習の意義は、学力を高めるだけではないのです。
ここでは、家庭学習がもたらす具体的な効果をお伝えします。
低学年だからこそ家庭学習が必要な理由
机に向かう習慣が付く
低学年のうちは、これが一番大きな目的だと言えます。
3・4年生、5・6年生になると学習内容がぐっと難しくなっていきます。中学生くらいになると、「テスト勉強」が当たり前になりますよね。
でも、勉強が難しくなってから勉強させようと思っても、うまくいきません。机に向かう習慣がないからです。
1日5分でも10分でも「机に向かう」という行為が、家で学習する習慣への第一歩なのです。
基礎的な学力を身に付けて、自信アップ
学校から出る宿題は、基礎的な内容が多いです。
特に低学年の学習内容は、3年生以上の学習の基礎となることばかりなので、基本をしっかり身に付けてほしいという学校側の思いがあります。
・3年生で学習する『わり算』には2年生の『九九』の知識が必須である
・習った漢字には(基本)教科書場にもふり仮名がふられない
ここで基礎が身に付いておかないと、その後の学習でつまずいてしまう恐れがあります。
学校で過ごす多くの時間が、学習する時間。「わからない」状態では、楽しくない時間が大半を占めると言ってもいいでしょう。
学習についていけないと「学校が楽しくない=行きたくない」と、不登校のきっかけになってしまう場合もあります。
▼行き渋りについての関連記事はこちら
計画を立てる経験になる
家庭学習に慣れてくると
「17時から20分勉強する」
などと、内容を自分で決めて取り組めるようになります。
はじめの頃は難しいので、親が主導で一緒に決めても構いません。
予定通りにいかないこともあるかもしれませんが、トライ&エラーを繰り返して、自分に合うペースを見付けられるようになるのです。
できることが増えて、生活が充実する
勉強をすることで、世界が広がるのは、子どもも大人も同じです。
漢字が読めるようになると、本が読めるようになります。辞書の引き方を覚えたら、自ら調べられるようになります。
このような、いいサイクルができていくでしょう。
一方で、勉強したがらない子どもに対して
「将来困るよ」
大人は、選択肢を広げるために勉強はしておいた方がいいと思えますが、低学年にとってはあまり実感のもてるものではありません。
低学年のうちは、その将来のために「机に向かう習慣が付いていてよかった」と思えるように関わることが大切です。
家庭学習の意味まとめ
家庭学習の時間の目安
一般的には「学年×10分」が家庭学習の目安と言われています。
ただし、これはあくまで一つの目安です。
現場で声を聞いていると、学校の宿題が「目安時間」ちょうどになる子もいれば、早く終えて余裕がある子もいて、個人差は大きいもの。
「机に向かった」ことが低学年にとっては大事です。
もし宿題だけで終わってしまっても、気にしないようにしましょう。
子どもが家庭学習をしたがらない理由とは?

「うちの子、全然勉強したがらなくて……」
家庭学習の悩みで、もっとも多い声のひとつです。
やる気がないように見えても、その裏には「がんばれない理由」が隠れていることがよくあります。
とくに低学年のうちは、まだ体力も感情のコントロールも未熟な時期。
まずは、子どもが「やりたくない」と感じる背景を知ったうえで、適切な関わり方を考えていきましょう。
子どもが勉強をしたがらない、よくある4つの原因
子どもが家庭学習に後ろ向きになる理由には、さまざまなものがあります。
ここでは、主に挙げられる原因を5つ解説します。
学校生活で疲れていて、体力が残っていない
授業・休み時間・給食・掃除……小学校生活は想像以上にエネルギーを使います。
中には学校からまっすぐ学童に行く子や、習い事をしている子も。
低学年は特に、まだ体力が追い付かない子が多いので、いざ始めようと思っても、なかなか勉強モードにならないものです。
宿題をしようと思っても集中できず、なかなか進まない、ミスが増えることなどにつながり、親子バトル…なんてこともありますよね。
遊びたいという気持ちが強い
外遊びやゲーム、おしゃべりなど、楽しいことが目の前にあると、勉強に集中しにくくなるのも自然なことです。
放課後は外に遊びに行きたい、勉強よりゲームがしたい、と学習を後回しにしてしまうケースはよくあります。
「宿題を終わらせてから遊びに行く」というルールを設けている家庭もあります。でも「全然言うことを聞かなくて…」と約束通りに進まずに、悩む保護者も珍しくありません。
わからない・難しいと感じている
学習に苦手意識があると「できないことに向き合いたくない」気持ちが強くなりがちです。
理解できないわけではなくても「なんだか難しそう」と思うだけで、気分が向かないこともあります。
勉強する意味がわからない
「勉強なんて楽しくない」
「なんで勉強なんてしなくちゃいけないの」
こう思っている子も多いです。
「できた!」「わかった!」と感動した経験が少なかったり、実感できていなかったりする場合があります。
これは、学校の授業で大体の内容を理解できる子にもみられる傾向です。
子どもの問題だけじゃない?親のかかわりが影響することも
自分のできない部分を知られたくない!という気持ちがある子は、なかなか家で勉強したがりません。
勉強している姿やプリントから「できないところ」が親に見られてしまいますよね。
子どもは親に「かっこいいところを見せたい」と思うものです。
また、×がつくことに強い不満をもつ子もいます。せっかく頑張ったのに「間違っている」と真正面から訂正されると悲しくなるのは理解できますね。
×をつけるのではなく、新しく枠を作って「もう一度書いてごらん」と声かけを変えるだけで、すんなり取り組めることもあるのです。
家庭学習をしたがらない子への関わり方

低学年が家庭学習の習慣を身に付けるためには、親のサポートが必要です。
でも、それは「無理やり毎日やらせること」ではありません。
家庭学習の目的は、「学びの習慣をつけること」。そのために、声のかけ方や環境づくりを工夫していくことが大切です。
まずは「なぜ勉強するのか」を一緒に考えよう
子どもが家庭学習を続けられるかどうかは「納得感」があるかどうかで変わります。
「前より速く計算できているね」
「できたものを先生に見せてみよう!」
など、勉強したことのよさを実感できるように、言葉にしてみましょう。
「宿題はやるのが当たり前」
といった声かけは、やる気を引き出す声掛けではありません。
大人も「やらされてる感」が強いとやる気が出ませんよね。
学びやすい環境を整えよう
家庭学習のしやすさは、環境で大きく変わります。
リビングや子ども部屋、音の有無などはその子によって合うスタイルは違うもの。
ここでは、これまで実際に効果があった具体的な例を4つ紹介します。
①静かな空間をつくる
視界に入るものも子どもにとっては刺激になるので、物を片づけて、気が散るものを見えなくなるようにしましょう。「目にも耳にも刺激がないように」がポイントです。
お手本にもなるだけでなく「おうちの人も頑張ってる」と思うと、子どもも集中モードになります。
自分で調べられるようになるまでは時間がかかるかもしれませんが、それが身に付くと一人での学習の進み方が変わります。

そんなときに、タイマーをセットしておくと「10分だけがんばろう」「音が鳴ったら終わり」など、気持ちの切り替えにつながります。
数字がカウントダウンされるデジタルタイマー、視覚的に時間の減りを実感するタイムタイマーや砂時計などを活用してみてください。
夕方に集中できない子は「朝活」もアリ!
「放課後は遊びたくて集中できない!」
そんな子には、朝の時間に5〜10分だけ勉強するのも有効。
朝はまだ頭がスッキリしていて、気が散りにくい子も多いです。
生活リズムにもよりますが、「朝頑張れば、放課後は自由」と子ども自身がメリットを感じるようになると、そのまま習慣付くケースがあります。
「やり方がわからない」タイプでも、ひと工夫で学習に向かえる
やる気はあっても、どう取り組んだらいいかわからない子もいます。
そんなときは、親の出番。
「いずれは自分でできるようになる」を目指した方法を3つ紹介します。
①問題を作ってあげる
そのときに問題の作り方も教えると、簡単なものは自分で作れるようになります。
「今日はこれとこれ、どっちやる?」と選択肢を与えてみましょう。
これは、実は親がサポートしているのですが「自分で決めた」ということがやる気を引き出したり、自信をもたせたりします。
③好きなものからスタートさせる
苦手なことばかりだと「勉強=大変、嫌だ」となるので「今日は何しようかな」という日こそ自由研究のように「好きな内容」に没頭するのもいい刺激になります。
絵本作りは字や文を書く勉強、ポケモン図鑑でもカタカナや漢字の勉強、というように、一見勉強らしくなくても、学習につながることは日常にあるものです。
やる気を引き出す声かけのコツ
✓小さなことでもしっかり褒める
「この字が特にきれいに書けてるね」
など、具体的に褒めることが大切です。
結果だけでなく、学習への姿勢や過程を認める声掛けだと「ちゃんと見てたこと」がより伝わります。
✓「教えて!」というスタンスで関わる
「教えてくれる?」
と、「できたこと」や「わかったこと」を質問してみてください。
子どもは勉強に関して「教わる」ことの方が多いので「教える」ことは新鮮に感じます。
「自分の学習内容に興味をもってくれてる」と思うと、やる気にもつながります。
また、覚えたことをアウトプットすることで、さらに理解を深めることにつながります。
勉強って楽しいかも!低学年でもできる「学びの工夫アイデア」

「楽しくないから、やりたくない」
これは、子どもが勉強を嫌がる理由の中でも、実はとても根本的なものです。
勉強の内容そのものよりも、「勉強=つまらないもの」と思いこんでいることが、やる気のブレーキになっていることも。
でも、勉強したことが生活につながるとわかれば、学習がぐんと身近なものになります。
生活に結びつけると関心がアップする
「これって勉強になるんだ」と感じられる体験は、子どもの「学びのセンサー」を育てます。
✓家の中にある数字やひらがなを探してみる
時計、カレンダー、冷蔵庫の中のパック、説明書など普段何気なく見ている物の中にも、数字やひらがながたくさん隠れています。
✓「ごっこ遊び」で、お金のやりとりや足し算・引き算を使ってみる
お店屋さんごっこでは「商品名」「個数」「金額」要素があります。
「お母さんは4つね。どっちが多い?」
こんな日常の会話も「算数」です。
ただ、「遊んで終わり」じゃなく「これが算数だよ」と教えてあげると「勉強って普段の生活につながるんだな」と実感をもつことができます。
✓家族の名前を書いてカードを作る
字を覚えたての頃は、家族の名刺カードを作る遊びも、学びです。
「漢字でも書いてみたい」
こんな言葉が生まれたら「学びのスイッチON」です。
身近なもの(家族の名前)から、一般的なもの(漢字の使われた方など)に学びを広げるチャンスになります。
ちょっとした工夫で「遊び×学び」に
遊びの延長で勉強に近づけて「もうちょっとやりたい」を生む作戦です。
✓親から子へクイズ形式で出題
子どもの音読の後に親が登場人物を答えるなど「逆バージョン」にしても盛り上がります。
✓「好きな〇〇」単語帳を作る
「勉強っぽさ」を感じさせないところがポイントです。
✓家庭学習ビンゴを作る
できたらシールを貼ろう!など声をかけて、コンプリートを目指します。
すべて埋めたらどうするかも話し合っておくとモチベーションをあげるのもおすすめです。
【こちらの記事では「机に向かわずにできる学習」を紹介しています】
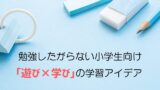
ごほうびの扱いにはちょっと注意
学校で子どもの声を聞いていると、
「ほしいぬいぐるみ頼んでるんだ」
など、ごほうびをモチベーションにしている様子が感じられます。
ごほうびシステムを全否定するわけではありませんが、扱い方には注意が必要です。
「ごほうびがもらえるからやる」という外発的動機が強くなると「学びそのものを楽しむ感覚」が育ちにくくなることもあるからです。
「学校では大丈夫?」家庭学習に不安を感じたときのチェックポイントと相談のコツ
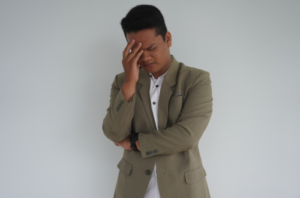
家庭での様子を見ていると「うちの子、大丈夫かな?」「もしかして学校でも困ってる?」と心配になりますよね。
ここでは、学校に相談すべきタイミングと、その伝え方をお伝えします。
学校に相談するか迷った時の基準
やる気の波はあっても、大きな拒否反応がなければ、心配しすぎなくて大丈夫です。
ただ、次のような傾向があるときは、一度学校と話してみてもいいラインです。
これは、学習そのものに困りを抱えているケースだと考えられます。
学校でも困りがある可能性が高いため、早めに情報共有しましょう。
学校では基本的に45分程度座っているはず。
10分座っていられないということは、教室でもじっとしていられなかったり、離席したりするなどのサインが表れているかもしれません。
このような姿を見ると、親も困りますよね。
学校ではできているのか、それとも拒否反応を示すのか、普段の様子を聞いてみましょう。
先生にうまく伝えるコツと、聞くべきこと
「こんなことで連絡していいのかな?」「家で何とかしないと」と思うかもしれません。
でも、先生に子どものことをより深く知ってもらい「一緒に考える協力の場」にすることが大切です。
ここでは、学校への聞き方を紹介していきます。
普段の様子を聞くことで、拒否する姿は家だけのものなのかを知ることができます。
家だけな場合と、学校でも拒否する場合とでは原因と対応が変わるので、重要なポイントです。
「何度教えても定着しない…」
こんなときは、教え方を聞いてみましょう。
学校の先生は、同じ学習内容でも子どもに合わせて色々なパターンで教えています。
また、「家でも学校でも同じように教わる」方が子どもにとっての安心感にもなります。
私自身、学習に困っている子の保護者と、その子に合った教え方を話し合いました。
後日「先生の言ってたやり方でやってたら、少し覚えてきました!」と言ってくださいました。もしそれが合わなくても、試行錯誤しながらよりよいアプローチを考えていけます。
家での様子を話すと、その状況にあった関わり方を教えてくれるはずです。
もしかすると、学校では実践しているかもしれません。
「○○が苦手そうなので、ここだけお手伝いしてみてください」
などと、私も話したことがあります。
まとめ|家庭学習は「できることから」が大事
小学生が家庭学習を嫌がるのは、よくあることです。「うちの子だけ…?」と心配になる必要はありません。
特に低学年のうちは、体力や気分の波、環境や声かけの影響を強く受けます。
大切なのは、毎日完璧にやらせることではなく、少しずつでも学びに向かう習慣を付けていくことです。
これまでご紹介したような声かけや環境づくり、アイデアを通して、子ども自身が「やってみようかな」と思えるきっかけを作ってあげられると、学習への気持ちも自然と前向きになります。
親も子も無理のない形で、家庭学習を「少しずつ」続けてみてくださいね。

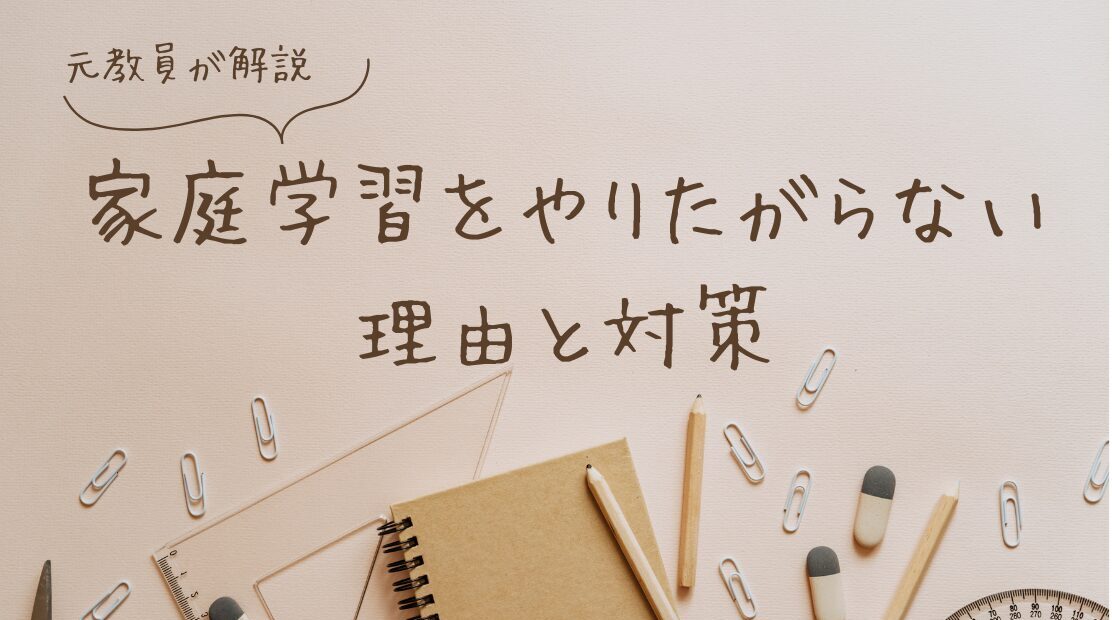
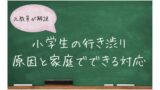
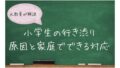
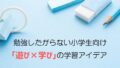
コメント